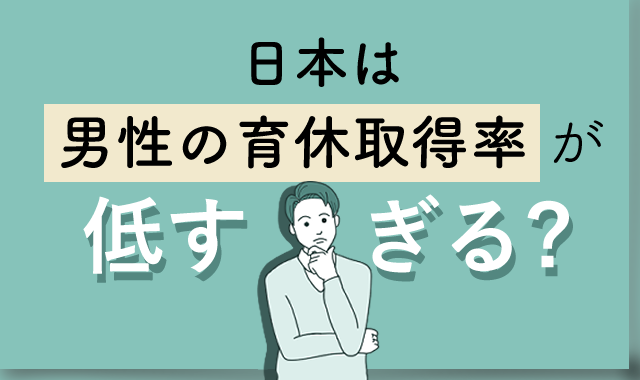こんにちは鎌倉OLのNっさんです。
日本でまだジェンダーの壁を感じるのことがあります。それが男性の育児休暇取得です。
日本とスウェーデンの育休取得率の比較
早くから男女平等の意識を持ち、労働時間短縮など労働環境が整っているスウェーデンの育休取得率は、2004年時点で、女性では8割強、男性では8割弱と、それほど差はありません。※
それに対して、2018年時点の日本の育休取得率は、女性では8割強、男性では1割未満(6.16%)。日本の男性の取得率は、とても低いです。

※補足
スウェーデンの男性の育休取得率は高いですが、両親が取得した育児休業日数の中で男性によるものは10%強のみです。
男性も取得はするものの、やはり女性の方が育児のために休業する日数が多いようです。
スウェーデンの育休制度
次に、スウェーデンと日本の育休制度を見てみましょう。
スウェーデンでは両親が合計で、通算480日(フルタイム勤務で約2年)の育休を取得することができます。このうち60日は、相手に譲ることができません。
また、480日のうち390日は育児休業により得られなかった給料の80%が保証され、残り90日は、定額給付となっています。
日本の育休制度
一方、日本では、両親ともに子どもが1歳(フルタイム勤務で、約240日)になるまで取得できます。(要件を満たせば、最長2歳まで可能)
開始から6ヶ月は賃金の67%、7ヶ月以降は50%が支給されます。
また、夫婦共に取得すれば、原則、1歳までのところ、条件を満たせば1歳2カ月まで取得可能になります。給付率も1年間ずっと「67%」となります。(この制度を「パパ・ママ育児プラス」といいます。)
「パパ・ママ育児プラス」について▼
(参考サイト:doda.jp)
夫婦二人で育児休暇を取るために「パパ・ママ育休プラス」を利用しよう
日本とスウェーデンの制度を簡単に説明しましたが、スウェーデンの方が圧倒的に優れている!というわけではないようです。むしろ、日本の育休制度も世界の中では恵まれている方と言われています。
なぜ、日本男性は育休を取らないのか
日本の育休制度は、夫婦共に取得すればメリットがあります。
(1歳2カ月まで取得期間延長。給付率が1年間ずっと「67%」など…)
それにもかかわらず、なぜ男性の取得率は低いのでしょうか?
下記の理由が考えられます。
❶ 男女の賃金差
❷ 「男が主要な労働力」という根強い固定概念
フルタイム勤務の男女の賃金指数を見てみると、男性100に対して女性70。女性の方が平均的に賃金指数が低いです。
そうすると、「どちらが育児を優先するべきか」を考えた際、平均収入の低い女性の方が育児のために休業する傾向が強くなります。
もちろん、夫婦共に休業できるのが理想ですが、休業によって収入が減る事を不安に思う人が多いようです。
徐々に、日本男性が育児休暇を取得するケースが増えてきたものの、やはり「男が育児休暇なんて‥」という古い固定概念が根強いことも確かです。育児休暇を取っても「1週間だけ」「1ヶ月だけ」など、短いケースも多いでしょう。
また、女性の場合は、お腹が大きくなるので、「彼女はそろそろ産休に入るんだな。」と周囲に認知してもらいやすいです。そのため、比較的スムーズに産休→育休に入るための準備ができるでしょう。
しかし男性の場合、自ら発信しない限り、あらかじめ引き継ぐ準備を始めることが、実際にはなかなか難しいのではないでしょうか。
加えて、ちょうど、育児世代となる20代後半から40代前半の男性たちは、職場の要として主戦力になりがちです。大きな仕事を任される事が多く、「穴を開けられない」という意識も強くはたらき、なかなか育休取得に踏み出せないのでしょう。
今後、男性も数ヶ月育休を取得するのがあたりまえの世の中になれば、職場全体で、男性の育休取得のために協力的になっていくのではないでしょうか。
実は育児をしたい男性たち
近年、日本の男性たちの意識も少しづつ変わり、「子供ができたら育休を取得したいか」という質問に対し、「取得したい」と回答する人が4割いるというデータが出ています。
▶︎参考サイト:PRITIMES.JP
【父の日】一般男性の家事・育児参加状況のアンケート(株式会社リクルートコミュニケーションズ/2017年)
育児を希望しているのに、なかなか休暇が取れないということが、日本の現状のようです。
自ら積極的に育児休暇を取得すること、また、それをサポートする職場づくりをすることが日本社会に必要でしょう。
イクメンは、もう古い?
確かにこんな世の中ですので、育児に積極的に参加している男性を見ると感心する人は多いでしょう。
2000年頃から「イクメン」という言葉が登場し、育児をする男性に対して使われるようになってきました。
しかし、2021年現在において、「イクメン」というのは過剰評価なのではないか、という疑問の声も増えてきています。

現在、共働きの世帯が増え、「夫婦で協力して自分の子供を育てる」ことが一般的になってきています。
それにもかかわらず、男性に対してのみ「イクメン!」と賞賛される傾向が今だに残っています。
これは、私たちが無意識に持っている「育児は男性より女性が当たり前だ」という古い固定概念から生まれているのかもしれません。
「イクメン」という言葉は、20年前に男性の育児参加に貢献してくれた素晴らしい言葉です。
しかし、今の時代で使用するには、少しの配慮が必要になります。